はじめに
この記事では、前回の初級に引き続き「立体図形の特徴と種類」を見ていきます。今回は特に、球や見取り図・展開図について解説します。
まだ初級の記事を読んでいない方は、先に下のリンクから読んでおくことをおすすめします。
→ 立体図形の特徴と種類(初級)
(所要時間:5~10分)
単語・表現の一覧
| 単語・表現 | 意味 |
|---|---|
| sphere | 球面 |
| ball | 球体 |
| solid sphere | 球体 |
| hemisphere | 半球 |
| diagram | 見取り図 |
| rough sketch | 見取り図 |
| net | 展開図 |
単語の解説
「球・球面・球体」についての英単語を解説!
1.球・球面・球体の意味の確認
私たちは普段「球」と「球面」、「球体」という単語を正しく理解せず使っていることが多いです。
そこでまずは、これらの意味を明確にしましょう。
| 名称 | 意味 |
|---|---|
| 球 | 「球面」もしくは「球体」を指す言葉で、数学では使われない単語 |
| 球面 | 球の表面だけを言う単語 |
| 球体 | 球面の内側も含めた空間全体を言う単語 |
2.英語でこれらに対応する単語は?
英語でも日本語と同じように区別されます。
球面は英語で「sphere」、球体は「ball」もしくは「solid sphere」と言います。
数学以外の場面で単に「球」というときには「ball」ということが多いと思います。

初級では「solid figure(中まで含んでいる立体図形)」と「3D shape(表面のみを表す立体図形)」の違いについて説明しました。
「球体(ball/ solid sphere)」と「球面(sphere)」はこれらの最も一般的な例です。
この考え方は実は平面図形でも考えられました。
例えば、円は「中心からの距離が等しい点の集合である曲線」を指しますが、円板は「円で囲まれた部分全体」を指します。
円は「circle」でしたが、円板は「disk」もしくは「disc」となります。

3.半球を英語で言うと…
半球は「hemisphere」と言います。
例えば、北半球は「nothern hemisphere」、南半球は「southern hemisphere」と言うことができます。
「hemi-」の語源は、「半分」を意味するギリシャ語の「hēmi」から来ています。
この語源は「semicircle(半円)」などで使われる「semi-」と同じです。
見取り図と展開図について
1.見取り図・展開図の意味の確認
小学校の算数では「見取り図」と「展開図」を習います。
まずはこれらの単語の意味を確認しましょう。
| 単語 | 意味 |
|---|---|
| 見取り図 | 点線などを使って立体の全体が分かるようにした図 |
| 展開図 | 立体図形を辺で切り開いた図 |
図を見れば思い出す人も多いでしょう。

2.見取り図を英語で言うと…
見取り図を英語で言うと「diagram」や「rough sketch」のような感じになります。
特に見取り図に対応した単語があるわけではないです。
しかし、「Please draw a diagram of a cuboid」と言われれば、長方形の見取り図を描くことになります。
日本人のほとんどは立体図形をきれいに描けますが、海外ではそうでない場合も多いです。
例えば、隠れた辺を点線で表さなかったり、線が平行に描けなかったりする数学科の大学生や先生がすごく多いです。
日本の小学校・中学校教育は、こんなところまで教えることに驚くことがよくあります。
3.展開図を英語で言うと…
展開図は「net」と呼ばれます。
例えば、「net of a triangular prism」は「三角柱の展開図」となります。
「net」には「網、くもの巣、ネットワーク」などのような意味があるように、展開図も多くの辺が繫がった形をしています。
このことから、「net」と呼ばれるようになったと考えられます。
算数で展開図を習う目的は主に「辺や面、点などの関係を調べることで立体図形への理解を深めること」です。
そのため、高校や大学に入るとほとんど使われなくなる単語だと思います。
記事のまとめ
| 単語・表現 | 意味 |
|---|---|
| sphere | 球面 |
| ball | 球体 |
| solid sphere | 球体 |
| hemisphere | 半球 |
| diagram | 見取り図 |
| rough sketch | 見取り図 |
| net | 展開図 |
最後に
いかがでしたか?
今回は覚える単語は少なかったのですぐに読めたと思います。ただ、球・球面・球体の違いなどは、細かいですが重要な部分なので覚えるようにしましょう。
次の第13章では、「図形で習ういろいろな性質」について解説します。最後まで読んでいただきありがとうございました。


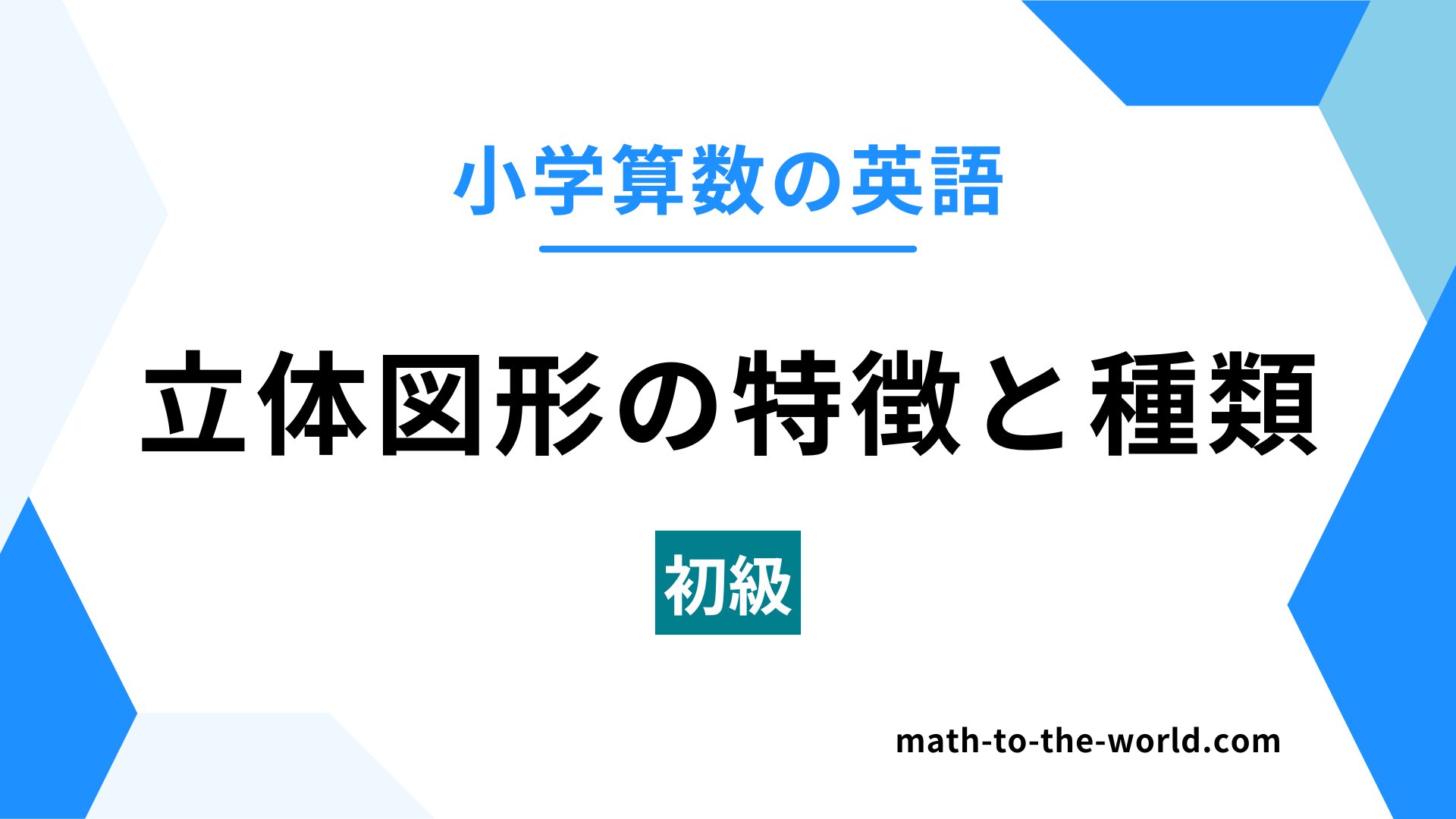
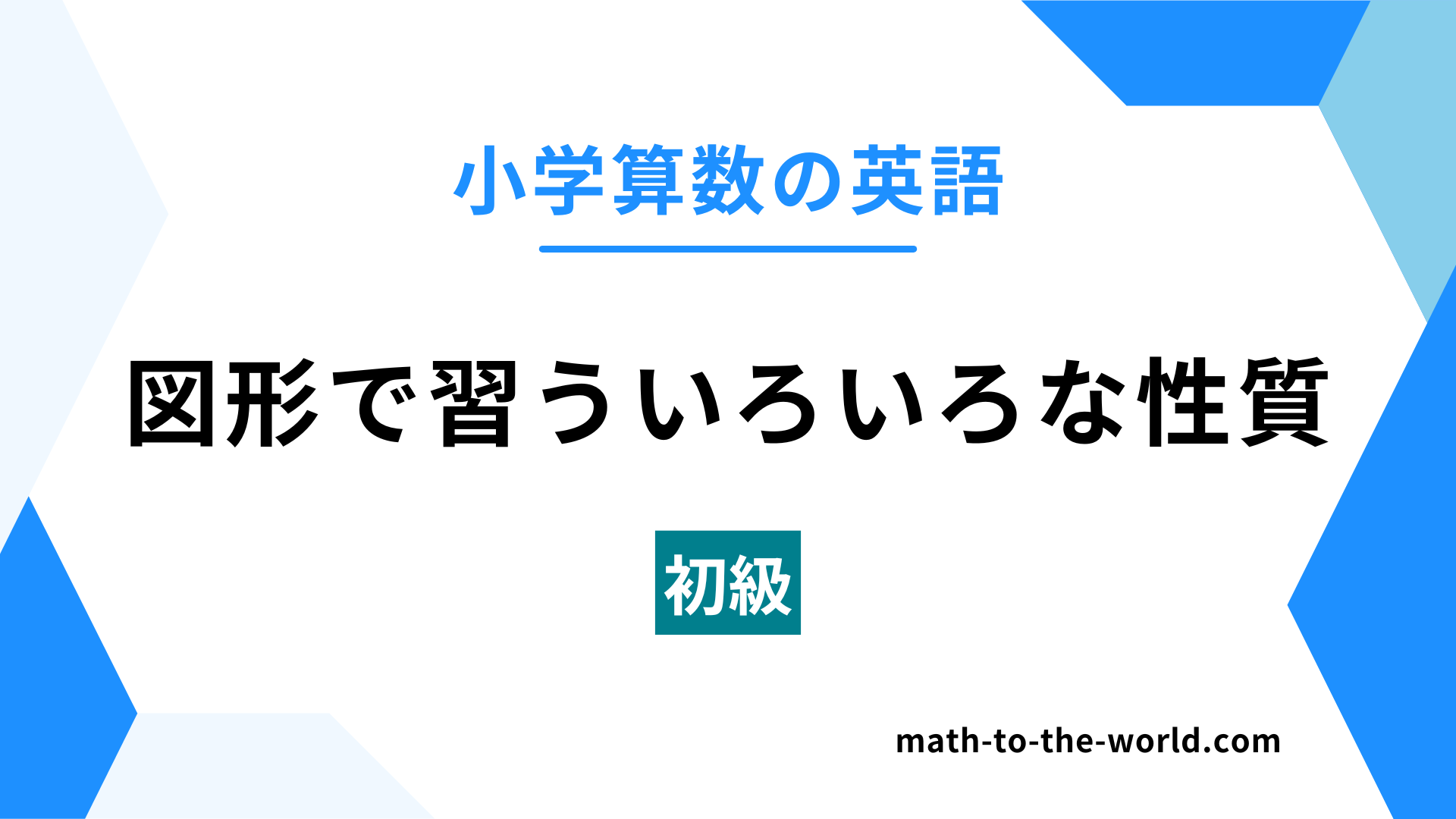
コメント